2010年10月08日
ABC Cooking 女性の心をつかむブランディングの軌跡

ABC Cooking Studio 女性の心をつかむブランディングの軌跡 著者:志村 なるみ
料理教室に関する企画を立てていたので、参考になると思って読んでみました。
料理教室と聞いて思いつくのが、ABC Cooking Studio。
たまたま図書館で見つけてすぐに借りて読みました。
スタジオのブランディングの思想と、創業からの軌跡と想いが綴られていました。

ABC Cooking Studioは、F1会員22万人、全国100店舗を誇る日本最大の料理教室。
女性の心をつかむマーケティング、宣伝費をかけない口コミの秘訣、99%をしめる女性社員の活用法、おしゃれな空間づくりなど女性向けビジネス成功のコツが詰まっていました。
もちろん、料理教室のノウハウも参考になるのですが、それ以上に著者の想いが素晴らしい内容でした。
まず、「日本一の会社をつくる!」という強い思いを胸に、二十歳という若さで起業した志村なるみさん。
元々は静岡の小さなキッチンツール販売会社の立ち上げから始まり、そのキッチンツールを販売促進のために始まったのがきっかけのようです。
つまり、キッチンツールというモノを売るために、料理というスタイルを提案していこうというものです。
すると、当時、想像を超えた反響があったようです。まさに、時代を先取ったマーケティングですね。
人材についても共感できるところが多く、採用時に気をつけるポイントは要チェック。
1.女性に好かれる女性であること
2.過去に大なり小なりリーダーシップの実績を持っている(「今から頑張ります」は信用しません)
3.採用の段階で、その人が数年後にスタジオマネージャーとして働いていることがイメージ出来る人材を選ぶ
おそらく、何人もの人を採用する中で体系的に抽出された項目だと考えられますが、このような著者の多大なる経験から生まれた理論を得ることができるというのが、読書の醍醐味だと思います。
さらに、「食生活の大切さを伝えていくことが健康な人間づくりへと発展していく」という理念を元に事業を拡大し、「格式高かったお料理教室を、一般女性が気軽に楽しめる場として提供したい」と進めていく。
思うに、これからの時代はやはり”共感”というのがひとつの大きい潮流になると考えています。
ABC Cookingが発信するメッセージに共感し、想いを共有しながら、そのパイ(母数)を広げていく。
ブランディングを、約束を守り続けることではないかと提唱しています。
この、守り、”続ける”という点がとても重要なのではないかと感じました。
”続ける”ためには、続けるための環境(人・モノ・コト・・・etc)が必要であり、それらを牽引していく情熱や想いなのかなぁと。続ける、というのは、言うは易し、行うは難し、ですね。
働くということは、上司に言われたことをこなすことではなく、1人ひとりが会社作りに参加すること。
本書では、それこそ淡々と描かれていますが、実像は私たちの想像以上にストーリーがあったのではないかと思いました。おすすめの一冊です。
2010年09月17日
シナリオ人生

ドラマは人生だ。

「シナリオ人生」 著者:新藤 兼人
1912年広島生まれ。1950年近代映画協会創立。映画監督・シナリオ作家。代表作は「裸の島」(モスクワ映画祭グランプリ受賞作品)、「原爆の子」「第五福竜丸」「午後の遺言状」「ふくろう」他、多数。日本のインディペンデント映画の先駆者であり、95歳の現在も現役監督・シナリオ作家として活躍中。70年に及ぶ制作活動において手がけた監督作品は47本、シナリオは240本以上。48本目の監督作品となる『花は散れども』の撮影準備が進行中。
長田の図書館でたまたま目にとまって読んでみました。
正直、20代の僕にとっては著者の作品を観る機会がありませんでした。
大河の一滴の脚本もされていたようなので、知っているとすればその辺りでしょうか。
それでも、長年映画の監督・脚本に携わってきて、92歳にして振り返る人生エッセイとしての読み応えは十分でした。
はじめのうちは、なんだか取っ付きにくい印象を受けるのですが、若い頃の苦労話は、今となってはかなり新鮮な内容でもあります。
貧乏と戦争と、さまざまな不幸に加え絶えざる研鑽ののちに、シナリオの極意に気づきます。
それは、どちらも発端、葛藤、終結の三段階で構成されます。
あらゆる名作を観ながら、見出したひとつの方法論。
当たり前といってはそれまですが、このような方法論は、長年の努力と経験の積み重ねによって見出され、当人の骨となり肉となり、血が宿るように感じました。
現像場の便所の落し紙に印刷された脚本を熟読し、小津安二郎、溝口健二、内田吐夢らの映画つくりから直接学んだドラマと人生の核心。
2010年現在、日本最高齢の現役映画監督であり、世界でもマノエル・デ・オリヴェイラに次ぐ位置にあります。
そんな新藤監督へのインタビュー記事があるのですが、それが非常に興味深い、というより、これは現代を生きる私たちは一読の価値はあると思ったので加えて紹介します。
僕は、いわゆる「戦争反対」と言っている人たちとは、少し次元が違うんです。32歳で召集され、戦争の中身を体験して帰ってきているわけですから。
僕が、戦争になぜ反対かと言うと、それは“個”を破壊し、“家庭”を破壊するからです。
・・・中略
要するに、一人の人間の権利なんて考えていません。しかし、実際に戦争を戦うのは、みんな個人なんだ。そして、ひとり一人の個には家族がある。
・・・中略
人間はどうやって死ぬかということは、人間の持っているひとつのテーマでしょう? 誰もが考えてますよ。できるだけ長生きしたいとか、ぽっくり死にたいとか、平和にやすらかに死にたいとか、家族や子供たちみんなに見守られて死にたいとか。そういうのは人間の大きなテーマなんですね。
それが、戦争によって取り上げられちゃう。人の一生の大切なテーマが、メチャクチャにされてしまうということです。
http://www.magazine9.jp/interv/shindo/shindo.php
070808 マガジン9~この人に聞きたい より
思うに、現場の体験者だからこそ作れるもの、それこそまさに新藤監督にとっての使命なのかもしれません。
信念を持ちながら、何かを創るという姿勢に大いに刺激を受けました。
過去の作品も見返していきたいと思います。
2010年09月16日
映画は撮ったことがない
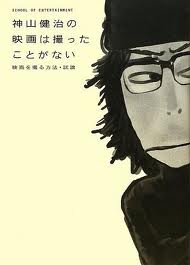
神山健治の映画は撮ったことがない~映画を撮る方法・試論 著者:神山健治
映画ブログというわけですが、本のレビューも書いていこうと思いました。
そこで、せっかくなので映画に関係するものを取り上げてみました。
『東のエデン』監督・神山健治が企画開発から仕上げにいたる作品作りの全工程を具体的に解き明かしたのが本書。映画制作の指南書としても読み応え十分であり、神山作品はもちろん、映画・アニメの鑑賞により深みを与えてくれることは間違いないです。
と、色々思索していると、アニメアニメで書評があるではないですか!
宮崎駿、押井守、大友克洋・・・1980年代に日本のアニメをアニメというジャンルに成立させ、そして現在、この分野の巨匠としてみなされる才能たちである。そこから20年以上の時が流れ、今やこうした監督たちを引き継ぐ新たな才能が求められている。
では、2009年以降、彼らを引き継ぐのは誰なのだろうか?
アニメに関心があれば、気になる人も多い話題だ。おそらくその中には、『パプリカ』や『千年女優』など海外で幾つもの映画賞を重ねる今敏や、劇場版『クレヨンしんちゃん』のシリーズや『河童のクゥと夏休み』の原恵一、そして『時をかける少女』で一気にアニメファン、映画ファンの心を捉えた細田守の名前が挙がるに違いない。
しかし、このなかに神山健治の名前を並べる人も少なくないだろう。
それは『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』で見せたドラマ性、揺るぎなく構築された近未来の舞台設定、『精霊の守り人』での豊かな物語、世界観の構築を見れば、納得の行くものだ。
・・・
本のもとになったのは、雑誌「STUDIO VOICE」で連載された同名のエッセイである。
・・・
2009年04月19日
映画『東のエデン』の前に読みたい 『映画は撮ったことがない』
http://animeanime.jp/goods/archives/2009/04/post_31.html
な、なんていい書評なんだと感心してしまいました(笑)
詳しくはリンク先を参照ください。
それはさておき、この本は単に映画に関係している人ではなくても、映画(アニメ)というひとつのコンテンツを作る過程において、ある程度の共通理解が得られるのではないでしょうか。
簡単にいえば、ジャンルは違えど、どの業界においても通じるものがあるということです。
個人的に興味深かったコンテンツは
特別対談:
×押井守
企画の正体
「良い脚本」とは
「演出の腕」を上げるために
編集の妙味とは
画コンテとカット割り
色彩設計
作家性なるモノ
です。
やはり、神山氏の師匠である押井守氏との対談は興味深い。
企画の正体では、映画を製作する上で、ある程度決定権のある人を説得できる(ここではプロデューサー)ことが重要であると述べられています。
私は代理店に近い位置づけで働いていますが、確かに、立場上の立ち振る舞いというのはとても重要です。
クライアント先、プロデューサー、ディレクター、デザイナー、プログラマー・・・
色んな人たちが集まり、ひとつのコンテンツを作っていく。
その中での流れや接し方(コミュニケーションも含めて)や考え方について、大いに共感できる部分がありました。
その他、脚本・演出の妙として、疑問の提示、それに対する解答・伏線の張り方、それを盛り上げる音響効果に色彩設定についての記述はとても参考になります。
例えば、ウェブで連載記事を書いているのですが、受け手に対して、疑問の提示(伝えたいメッセージに言い換えられますが)を行いますし、記事の内容によって色彩(デザイン)を考えたりします。
作家性なるものでは、作り続けていれば、ある程度一貫したものがみえてくる。
それが作家性ではないかと・・・
これからも、とにかく作り続けて、日々を切磋琢磨していきたいと思いました。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリ
最近の記事
マクロスF 恋離飛翼〜サヨナラノツバサ〜 (4/24)
須磨離宮公園に行きました (2/27)
猫の目線で撮ってみる (2/14)
森村泰昌企画展、鑑賞。兵庫県立美術館へ行ってきました (2/11)
パーマネント野ばら (2/9)
告白 (1/25)
寄り道家のすすめ (1/23)
かもめ食堂 (1/16)
京都”山部”新年会 (1/11)
2010年、映画個人的にベスト5! (12/31)
恋愛寫眞 (12/28)
8月のクリスマス (12/25)
マイブーム (12/22)
手紙 (12/14)
スラムドッグ$ミリオネア (12/13)
ルミナリエ撮影 (12/13)
イヴの時間 劇場版 (12/9)
トイ・ストーリー3 (12/6)
アニメーション神戸に行ってきました。 (12/1)
休日の過ごし方 (11/29)
過去記事
最近のコメント
在本桂子 / 瀬戸内国際芸術祭~直島、犬島
いぶすきー / 瀬戸内国際芸術祭~直島、犬島
在本桂子(犬島) / 瀬戸内国際芸術祭~直島、犬島
竹村竹子 / 須磨離宮公園に行きました
いぶすき- / マイブーム
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
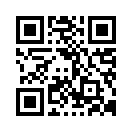
アクセスカウンタ
読者登録

